延喜式内社を巡る(その2)
延喜五年(905)から編纂が開始され、延長五年(927)に完成し、康保四年(967)に公布された『延喜式』に収載された「神名帳」に基づく、当時の朝廷が幣帛を奉献するとされる、いわゆる「延喜式内社」ですが、北は現在の岩手県中部、秋田県中部、南は鹿児島県の屋久島まで現在の鎮座地が分布しています。
なお、「奉献するとされる」としたのは、『延喜式』の前後の時代は、既に律令制度のほころびが全国に広がっていたからで、果たして「式」に定めた通りにそのような祭祀や奉献が行われていたのかは疑問が残るからです。この点については次回以降に詳しく述べます。
いずれにしろ、鎮座地の分布域が岩手、秋田から鹿児島に至るまでの地域に限られることは、平安時代の朝廷の威令が及ぶ範囲がその地域内であったことを示します。つまり、北海道や青森は蝦夷地であり、沖縄は琉球の地でした。
既に述べたように、延喜式内社は、時代の変遷の中で、自然の災禍や戦乱等によって鎮座地の移動がなされた遷座が数多く見られますが、それでも概括的には、港や官衙のある平地から河川の流域に沿って、現在の平野部の農村地帯、中山間地と遡り、流域の先端部にあたる水源地帯や神奈備山へと鎮座地が連なります。
延喜式内社を巡るということは、北海道、青森、沖縄を除く全国を、くまなく、しかも主要な河川の流域に沿って、都市部から中山間地の奥地に至るまで、一つ一つ辿るということにほかなりません。
後述しますが、幸いにも、昭和から平成にかけて「式内社研究会」によって編纂され皇學館大學から出版された全二十五巻の『式内社調査報告』により、現在の鎮座地などの情報がまとめられましたので、それを礎として一社一社をお訪ねしたということになります。

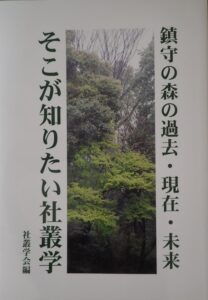

式内社を多く巡られた知見を是非ご教授いただきたいと思いました。まだまだ勉強中ですが、日本文化の基層として、地域ごとの文化を知る上で重要であるとの認識のもと、なるべく地域計画を進める上で把握するようにしております。しかしながら断片的で体系化できてはおりません。
奥深く興味深く今後学んで参りたいと思います。
富永さま、返信が遅れました。ご覧いただきありがとうございます。フェイスブックページもございますので、そちらも併せてご覧いただけると幸いです。
http://www.facebook.com/chinnjunomori
鎮守の杜にご興味をお持ちですか?延喜式内社などの古社は比較的に中山間地に鎮座をしております。限界集落も多く、ここ十年程度で奉斎する人もいなくなり、消滅する可能性もありますね。
Woah! I’m really enjoying the template/theme of this website. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s challenging to get that “perfect balance” between user friendliness and visual appeal. I must say you have done a superb job with this. In addition, the blog loads very quick for me on Safari. Excellent Blog!
コメントありがとうございます。Facebookpageもありますので、ご覧いただけると幸いです。
http://www.facebook.com/chinnjunomori